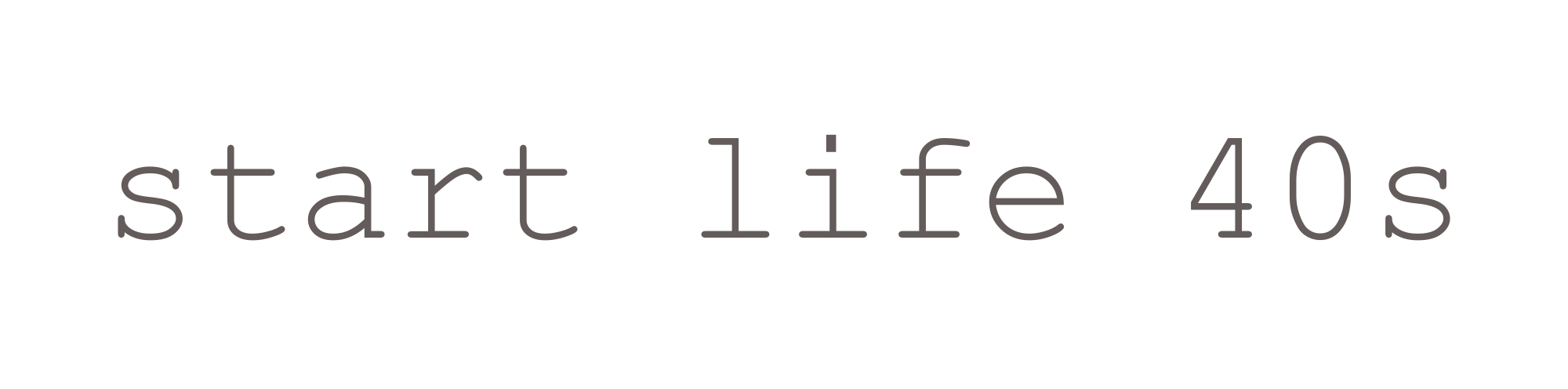鑑賞記録(2022.2.21)
カール・テオドア・ドライヤー監督
遺作
『ゲアトルーズ』1964
@元町映画館

(↑今回のチラシ)
”奇跡の映画
カール・テオドア・ドライヤーセレクション”
にて、上映4作品
『裁かるゝジャンヌ』『怒りの日』『奇跡』『ゲアトルーズ』
19世紀末にデンマークで生まれ、常に独創的で革新的な作品を生み出しながら、一貫して人間、特に女性の心の真髄をフィルムで捉え続けた、孤高の映画作家カール・テオドア・ドライヤー。ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー、イングマール・ベルイマンなどの巨匠たちからアルノー・デプシャン、ギャスパー・ノエといった現代の先鋭たちにまで多大な影響を与え世代を超え敬愛されています。79年の生涯で長編14作品を発表、モノクロームの世界を巧みに操り、新たな映画芸術の可能性を示し続けました。今回は、ゴダールが『女と男のいる舗道』で引用したことでも有名な『裁かるゝジャンヌ』と後期3作品がデジタルリマスタリングされ、スクリーンに甦ります。(チラシより抜粋)
今回は、
『ゲアトルーズ』を鑑賞。
(鑑賞4作品目)
『ゲアトルーズ』1964/118分/デンマーク(デンマーク語)/モノクロ・ヴィスタサイズ・2Kレストア/モノラル
原作はスウェーデンの作家、ヤルマール・セーデルベルイの同名戯曲。(スウェーデン語では「イェトルード」)
ドライヤーはかつて、無声映画の時代に「ゲアトルーズ」に関心を抱き、これを映画化しようと思ったことがあったが、台詞の多いこの劇は無声映画化することが困難で、この映画化の野望を諦めたということがあった。1962年になってステン・レイン(セーデルベルイの研究者)の研究に触れ、ドライヤーは再びこの戯曲に対する情熱をよみがえらせた。(本企画のパンフレットP.30-31より引用抜粋【解説:小松弘(映画史家)】)
愛を探し求め続けたゲアトルーズの姿を完璧な様式美の画面におさめ、会話劇に徹したドライヤー遺作にして集大成的作品(チラシより抜粋)
原題
Gertrud
受賞
ヴェネチア国際映画祭(1965)
国際映画批評家連盟賞
一言あらすじ
弁護士の妻ゲアトルーズ(ニーナ・ペンス・ローゼ)は、今はもう夫グスタフ(ベント・ローテ)への愛を持ち合わせておらず、若き作曲家エアラン(ボーズ・オーヴェ)に心が移っていた。ゲアトルーズは愛情はないと夫に告げ、エアランと暮らすつもりでいた。そこへ元恋人の著名な詩人ガブリエル(エッベ・ローゼ)が故郷に戻ってきて、ゲアトルーズと再会する。ガブリエルは昨夜ひどい話を聞いてしまったと話し・・・
感想
ネタばれですが・・・・・
愛がすべてと語るゲアトルーズが
さまざまな愛を経て
ひとり孤独に生きていく。
愛していると告げる
夫グスタフも、
詩人ガブリエルも、
結局は仕事を優先し、
自分を大事にはしてくれなかった。
だから私は去るのだと。
さらには、
愛しているエアランからは、
愛していないと告げられる・・・
一人、旅に出るゲアトルーズ。
長い月日が経ち、
彼女は一人暮らしている。
友人(?)のアクセルとは
長年続いていたが・・・
カール・テオドア・ドライヤーが描く
女性たちは
正直で意思が強い。
正直すぎるほど、
そして
強すぎるほどの意志。
自分に正直に生きている。
それが一見、
いわゆる不幸を招くとしても。
彼女が求めたのは
完璧すぎる愛だったのかもしれない。
気になる点は、
『奇跡』(1954)と、
同様に
ほとんど目線が交わされないところ。
(『怒りの日』(1943)もそんなところがあったが。)
愛しているエアランと
見つめ合う場面も
私には
なんだかゲアトルーズが
本当に見ているのかな??と、
ちょっとわからなかった。。。
これは、何を意味するのか・・・
(もう愛していない夫や元恋人に対してならわかるが)
毎度、私の浅はかな考えでは
全然理解しきれていないが、、、汗
また少し時間を置いて
観たい作品だ。
名作は大抵そうだと思う。
(2022年2月22本目。本年度59本目、映画館16本目)
スタッフ
監督・脚本・編集:カール・テオドア・ドライヤー
原作:ヤルマール・セーデルベルイ 『ゲアトルーズ』(『イェトルード』)
撮影:ヘニング・ベンツセン 舞台美術:カイ・ラーシュ 衣装:ベーリット・ニュキェア
他
キャスト
ゲアトルーズ:ニーナ・ペンス・ローゼ
グスタフ・カニング:ベント・ローテ
ガブリエル・リズマン:エッベ・ローゼ
エアラン・ヤンソン:ボーズ・オーヴェ
アクセル・ニュグレン:アクセル・ストレビュ
他